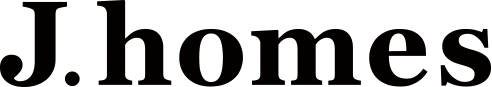大開口、大空間、吹き抜けのある間取りのメリット・デメリット【注文住宅】

住まいに開放感のある明るい空間をもたらす「大開口」と「大空間」を取り入れた住宅デザインは、注文住宅を検討されるお客様に人気の間取り、設計です。
特にリビングは、広がりを感じられる気持ちのいい空間にしたいですよね。キッチン、ダイニング、リビングをひとつながりにした大空間に、高天井の大開口が出来れば、開放感のあるおおらかな暮らし、家族と過ごす場所に自由な距離感と贅沢な時間が生まれます。
ジェイホームズでも、リビングからウッドデッキへ横につながる空間や、吹き抜けを設けて縦につながる空間といったアイデアを間取りに取り入れて、大空間・大開口の住まいをご提案、施工を行っております。
大開口・大空間特集では、ジェイホームズの施工事例を紹介しています。
このコラムでは「大開口・大空間」を設けて、採光や風通しの良い快適なリビングを実現しながら、耐震性といった安心・安全を重視した設計・施工のポイントをお伝えします。
目次
大開口、大空間に向く住宅、向かない住宅
最初にコラムのテーマを二分するような見出しですが、大開口、大空間に向く住宅、向かない住宅はあるのでしょうか?
大開口、大空間に向いている住宅は、基本的に面積が広めの住まいで、間取りにもゆとりがある住宅です。大空間を実現するには、デザインと構造を両立させる必要があります。
都市部で大開口の住宅を実現するには、外構の工夫や外観のデザインなどで、プライバシーを確保することが前提です。光や風を大胆に取り入れながら、道路や隣地からの視線を気にすることなく、大開口の窓に広がる豊かな外部空間を楽しめるようにする設計が求められます。
大開口のある住宅では、パッシブデザインをどのように実現するかもポイントになります。大きな開口部があることで、日射取得は有利ですが、日射遮蔽のために外部に庇を設けたりする配慮が必要です。
反対に大開口、大空間に向いていない住宅は、比較的面積が狭い住まいで、敷地状況からプライバシーを確保することが難しい場合です。
狭小住宅の場合でも、間取り次第ですが小さくても吹き抜けを確保し、隣接する住宅の開口部との関係性を確認しながらその吹き抜けに面する部分だけでも開口部を確保することで、住宅内部に光や風を取り入れる設計も可能です。
大開口、大空間、吹き抜けのある住まいで間取りを決めるポイント
「新築住宅のリビングはより広いほうが良い」と思う傾向がありますが、リビングは家族が一緒に長い時間を過ごす場所です。家族の人数を考慮しながら、リビングに求められる広さを検討することがポイントです。
まず、団らんするスタイルや、家具・インテリアのサイズ、レイアウトに応じてリビングに必要なスペースを決めます。ライフスタイルや持ち物の量から、収納のことも忘れずに考慮に入れて検討しましょう。
もし、敷地面積の都合でリビングの広さを十分に取れない場合は、吹き抜けやリビング階段を設置して視界を広げるデザインがおすすめです。
リビング階段は、「スケルトン階段」がおすすめです。スケルトン階段とは、踏み板とそれを支える骨組みだけで構成されています。段と段の間の板(蹴込み板)がないのが特徴で、「オープン階段」とも呼ばれます。
スケルトン階段は、そうしたデザインにより、圧迫感がなく、室内に入り込む光を遮らないという特徴があります。せっかく明るくしようと吹き抜けにしたのに、通常の階段では奥の空間まで光が入りにくくなるといった問題点を解消してくれるのです。
リビングに吹き抜けを作るメリットとデメリット(理由と対策)
リビングに吹き抜けを作るメリットとその理由
・空間に広がりを与えられ開放感が増す
明るく開放的なスペースにするために、吹き抜けは大きなメリットをもたらしてくれます。吹き抜けは、一部分とはいえ部屋の間取りが「縦」に合体したつくりで、合わせて窓を大きく取るケースもあるので、空間に広がりと開放感を与えてくれます。
・採光を取り入れ、室内を明るく見せることが出来る
近隣の住宅事情や土地の向きなどによって、窓を作っても光を取り入れることができないケースがあります。そうした場合には、吹き抜けとその吹き抜けに面した開口を設けることで、室内に光を入れることができます。
・冬も明るい空間を作れる
吹き抜けは、太陽の角度が低くなる冬場でも、近隣の家が近く太陽光が2階部分にしか入らないときにも、明るさ確保のために有効なつくりです。太陽光は、私たちに気持ちよさを届けてくれるだけでなく、健康をももたらしてくれます。
・狭小住宅であっても視覚的に広く感じられる
狭小住宅であっても狭さを感じさせない工夫のひとつとして、吹き抜けが利用されることがあります。寝室などプライベートな空間は狭くても良い、しかしリビングだけでも広く作りたいといったケースで利用される手法です。
リビングに吹き抜けを作るデメリットと対策
・冷暖房の効率が下がる、光熱費が高くなる
暖房効率が悪くなりがちで、暖房ではリビングで暖めた空気が天井へ登ってしまい、冬は寒い家になってしまいかねません。
<対策>
吹き抜け上部の天井面にサーキュレーションファンを設けて、上部の暖かい空気を空間内で対流できるようにしましょう。また住宅全体の断熱性能が高くなければなりません。住宅全体が温かい状態を保っていられれば、熱のロスを最低限にすることができます。
・掃除がしづらい、メンテナンスに手間がかかる
2階部分の開口部が1階の床面から高い位置にあることで窓が拭きにくい、吹き抜け上部の天井に付ける照明器具は掃除や電球の交換などを考慮しなくてはなりません。
<対策>
間取りやデザインとの兼ね合いですが、吹き抜け部分に「キャットウォーク」と呼ばれるメンテナンス用のスペースを設けることも対策の一つです。照明器具については、天井面に付ける照明器具だけでなく、壁側にスポットライトを設置して天井面や床面を上手に照らすことも可能です。
・強度面の心配
外壁面の開口部が大きいことや、床の大きな開口部となる吹き抜けは、広さを感じさせることと同時に、建物の強度を確保する上では不利な要素になります。
<対策>
大開口、大空間を実現するためには構造的な問題を解決しなければなりません。耐震性能の強化について次の項目で詳しく説明します。
耐震性に優れた大開口、大空間を「SE構法」で実現する
耐震性の高い木造住宅は柱や壁が多いイメージがあるかもしれませんが、現在の日本では耐震性にすぐれた木造の構法が開発されています。それが「耐震構法・SE構法」です。
SE構法を採用すれば、内部に柱や壁の少ない大空間の家をつくることも夢ではありません。大空間の家は、家族やライフスタイルの変化に合わせて間取りを自由に変えていくことができます。
木造でありながら、高い強度を実現できるSE構法であれば、大開口や大空間、吹き抜けを設けたとしても強度面の心配はありません。全棟で構造計算を行いますし、中大規模の商業施設や公共施設などの木造建築でも採用されるほどの強さを持っています。
SE構法は、柱や梁そのものを互いに剛接合し、強固な構造躯体をつくり上げます。構造計算によってあらかじめ地震の揺れや風の力を予測し、それに耐えうる性能を持った住宅づくりを可能にしています。住宅は、土地の周辺環境や立地条件によって1棟1棟異なるため、SE構法では全棟を構造計算しています。
SE構法は、性能が明らかな接合部や安定した品質の構造用集成材の部材を用いることで、構造計算やプレカット、施工精度、性能保証までを実現した「システム化された木造ラーメン構法」です。

<まとめ>
木の持つ温かみを感じさせながらも、広々としたリビングは、家族が集う場として快適で落ち着きのあるコミュニケーション空間となります。
しかし、構造的な問題を解決しなければならない大開口、大空間は、耐震性の高い耐震構法SE構法を採用するなど、性能面でも安全に、安心できるしっかりとした設計、施工が重要です。
ジェイホームズには、お施主様の「大きな開口、大きな空間を木造で」とのご希望を、その理想の通りに実現した施工実績が数多くあります。設計から、施工までプライドとこだわりを持ち、デザイン性、耐震・安全性、快適性を備えた家づくりを心がけています。
大開口、大空間の住宅デザイン、設計・施工のご相談やご質問は、お気軽にフォームから、またはお電話でのお問い合わせをお待ちしております。